
みなさんどうも、こんにちは!
僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。
2016年リオオリンピック。この大会でアメリカ代表として参加した長距離ランナー。彼の名前はメブ・ケフレジギ。


そして、驚くべきは彼の年齢です。
なんと41歳。41歳で選考レースを勝ち抜きアメリカ代表の座を手にしました。
さらに、同じくリオオリンピックの女子自転車競技でも女子史上初の3連覇を達成したクリスティン・アームストロング。彼女も当時、43歳。若者たちが台頭している中で3連覇という脅威の記録を打ち立てました。

また、陸上男子100m走での最年長メダリスト。ジャスティン・ガトリン。彼がメダルを獲得したのはなんと34歳。
伝説的スイマーのマイケル・フェルプスも31歳の時に金メダルを獲得し、驚くことにその3日後、アメリカの35歳、アンソニー・アービンが同種目、男子50m自由形で優勝し、その記録を打ち破りました。


この世の常識、エリート選手において、ほとんどの競技でのピークは20代
今回はアメリカのやり手、ジャーナリストであるジェフ・ベルコビッチが書いたこの本。
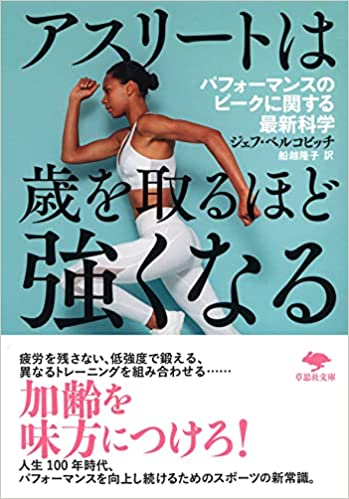
「アスリートは歳を取るほど強くなる、パフォーマンスのピークに関する最新科学」から歳をとっても活躍できるその秘密を紐解いていきたいと思います。
このブログを最後まで見ると、何歳になっても最高のパフォーマンスを発揮できる、そのノウハウがわかる!

是非、最後の最後に紹介するトレーニング理論までご覧ください。
目次
アスリートは歳を取るほど強くなる、パフォーマンスのピークに関する最新科学
その理由
あえて、あげるとするとこの3つです。
②タンパク質とゼラチン
③チャンキング
①トレーニングの簡略化(メンテナンスプラクティス)
まず、一つ目のトレーニングの簡略化(メンテナンスプラクティス)。

最も成功するアスリートとはどんなアスリートなのか?
それは、最もハードな練習をする選手。
ではなく、怪我の原因となる疲労の蓄積を上手く避ける選手です。そう、トレーニングによるストレスには実はふたつの側面があります。一つの側面が有益なストレス、もう一つの側面が有害なストレスです。
この二つの違いをちゃんと把握しつつ、
有益なストレスを最大に活用し、有害なストレスを最小限にとどめられる選手こそが、最も成功するアスリートである
と本書では指摘されています。
体力が落ちた、だからこそハードな練習、きつい練習ですべてをカバーしようとすると、最悪、故障を繰り返し引退を早めてしまいます。
だからこそ、賢いコーチというのは鬼のような練習メニューを課すコーチではなく、言葉を換えると、選手が故障するか?しないか?ギリギリのラインをせめるコーチではなく、パフォーマンスを低下させることなくどれだけ少ないトレーニングで効果を上げられるのか。そんな考え方が出来るコーチです。
ランニングで言えば、まさしく世界一の指導者との評価を得た中長距離の伝説的なコーチ、運動生理学者でもあるジャック・ダニエルズ博士。
この動画で解説している通り、彼が提唱しているダニエルズ式トレーニングなんかはかなり上手に負荷がコントロールさせています。
実際に先ほどご紹介したオリンピックに出場したアメリカ最年長マラソンランナー、メブ・ケフレジギ。
彼はこう言っています。
境界線はね、ごく細いんだ。そのほんのちょっと下くらい、トレーニングがほんの少し足りないくらいがいい。
この言葉の真意。それはトレーニングのどの時点でもう一度走れば逆効果になるかを知っているということ。つまりやりすぎは禁物であり、彼がこの歳まで現役で活躍出来ている秘密の一端です。
そう、エリート選手が、そのスポーツのピーク年齢を過ぎても活躍し続けているのは、トレーニングを増やしているからではなく、効率よくトレーニングをしているからなのです。
さてさて、よく耳にするこの効率的というとても曖昧な言葉。スポーツに関係なく仕事や勉強においても使うこの言葉。
1996年、認知心理学者のアンダース・エリクソンとラルフ・クランプは、熟年のプロピアニストは、若いライバルと比べて、週のうちにピアノに向かう時間が半分以下で同じレベルのパフォーマンスができると報告しました。具体的には、年長ピアニストが10.8時間に対して、若者は26.7時間です。
この研究から導かれるひとつの真実として、一度あるレベルまで到達した人であれば、そのレベルを維持するための練習時間をかなり減らせるということです。これをアンダース・エリクソン博士は「メンテナンスプラクティス」と呼びました。

これが効率的と呼ばれるもののひとつの正体です。
また、スポーツ心理学者のジャネット・スタークスは、マスターズ陸上競技のアスリートたちを調べ、スポーツにおいても同じ結論に達しました。

その驚くべき実例こそが、2012年ロンドンオリンピックの体操男子つり輪で入賞を果たしたブルガリア出身のヨルダン・ヨブチェフ選手です。
彼はなんと、「1週間」に90分間のみの練習に限定し、オリンピックで入賞を果たしたのです。
当時、彼は39歳、タイムズ紙のインタビューにおいてこう語っています。
それが手術をして治した肩が耐えられる限界だった
このように過去に積み重ねてきた技術があると、練習時間が少なくとも能力の維持は比較的簡単に行える。傍から見れば、効率的に見える。これがエリクソンの言うメンテナンスプラクティス、効率的という言葉の本当の意味です。

これが歳をとってもハイパフォーマンスを維持できる秘密のひとつの答えです。
②タンパク質とゼラチン

なぜ歳をとっても第一線で活躍し続けられるのか?
その理由、二つ目がタンパク質とゼラチンです。

FCバルセロナ、ラボバンク・サイクリングチーム・英国オリンピック委員会を含む多くの世界のトップチームにアドバイスをしてきたスポーツ栄養士で生理学者のアスカー・ジューケンドラップ博士はこう指摘します。
違いがありそうな証拠がたくさんある領域がひとつある。それは筋肉量を維持することについてで、タンパク質の合成と関係があるんだ。
さらにこう続けます。
加齢とともに、タンパク質の代謝にいくらかの変化が生じるんだ。同化抵抗性と言って、筋肉の量を増やすことに少しずつ抵抗が生じるようになる。
つまり何が言いたいかと言うと、誰であれ、歳を取るにつれてタンパク質を取り込み、再度、筋肉として組み立てる能力が低下するため、タンパク質自体の摂取を増やさなければならない、ということです。
おすすはアミノ酸のロイシンが多く入っている、鶏肉、牛肉、魚、大豆、チーズなどを食べることです。

これを聞いて、お皿に載った肉や魚の大きさを倍にする必要はありません。
ジューケントラップ博士によれば、タンパク質を摂るタイミングが、量と同じくらい重要なのだそうです。
彼はこう言っています。
一度に25g以上のタンパク質を摂取しても、ただ余分な尿素、つまり尿として排泄されるし、腎臓結石の形成に役立つ副産物を生成することにつながるだけだ
だからこそ、おすすめなのが、少なめなの量のタンパク質を3時間ごとに1日を通して食べることです。
さらに、これには思わね効果もあります。
ジョンソン&ジョンソン・ヒューマン・パフォーマンス研究所の運動生理学主任のクリス・ジョーダン博士によれば、
何でも食べるものにタンパク質を加えると、血糖値を下げる効果がある
とも指摘しています。
一度に大量のタンパク質を補給するのではなく、出来る限り細切れで摂取する。これが現時点でのスポーツ栄養学での正解のようです。
また、よく聞くプロテイン(タンパク質)摂取のゴールデンタイム。俗にいうトレーニング後30分以内が効果的。
実はこのようなゴールデンタイムは存在しないと主張する論文も発表されているくらいです。くわしくはこちらの動画で解説しています。
【本当に効果あるの?】プロテイン、水分補給、サプリメント、アイシング、ストレッチ
くわえて眠りにつく前に摂取したタンパク質は、タンパク質合成の強化に特に効果がある、という説得力のあるデータがあるため、ベッドに入る前に、温かいミルクを1杯飲む習慣も効果的であるかもしれません。
さらにあとひとつ、特に熟年アスリートにとってかなり有望に思える栄養分があります――それが、ゼラチンです。

スポーツのための栄養素としてゼラチンを推奨している中心人物は、カリフォルニア大学デービス校の生物学者であり運動生理学者のキース・バール博士です。
正直、本当なのか怪しいところではありますが、実際に最近の研究では、ゼラチンを摂取することで、さまざまな軟部組織の怪我の予防と治癒に役立つという報告があったり、怪我でリハビリをしている期間中にゼラチンを食べると、前十字靭帯の再構築、アキレス腱切断後のプレーへの復帰を早めるという結果をもたらすこともわかっているようです。
キース・バール博士は、コラーゲンの生成を最大にするために、トレーニングを行う1時間前に一定量のゼラチンを摂取することを勧めています。
このように食生活にも気を配ることで歳をとってもハイパフォーマンスを維持出来るのかもしれません。

キース・バール博士はゼラチンの摂取方法について、どんな形(フルーツゼリー、スムージー、カプセルなど)でもOKと言っています。
③チャンキング

なぜ歳をとっても第一線で活躍し続けられるのか?
その理由、三つ目がチャンキングです。
このチャンキングとは、関連した複数の出来事をひとつのパターンにまとめることです。このチャンキングにより、細切れになった情報を別々に処理するより、格段と意思決定のプロセスを簡略化、高速化することが出来ます。

たとえば、天才サッカー選手、リオネル・メッシ。
2014年のワールドカップの測定データによると、ゴールキーパーを除けば、プレー時間対比で走った距離を調べると、メッシが一番短かったことがわかりました。
同じポジションをプレーする他の誰よりも走行距離が少ないという事実。

これこそがチャンキングの真骨頂です。
簡単に言うと、次に起こることがわかるという予測能力・推測能力のことです。
アイルランド人のサッカーアナリスト、ケン・アーリーは、メッシが、プレーの流れを読む超人的な能力で、ボールがどこにおさまるかを予測することによって歩数を節約しているのではないかと推測しました。
この超人的能力こそ、チャンキングがなせる技。この選手がこう反応したから、ここにボールがくるなど、目の前の情報をパターン化して、頭の中にあるデータベースを参照し、意思決定のプロセスを極限まで短くするすべ。試合での流れを読む目。プレーを俯瞰できる能力。
だからこそ、NFLやNBAなど他の競技のスーパーアスリートたちはこういうのです。
起こるであろうことが、起こる前に見えた
とか
それがスローモーションのなかで起こったように感じた
などです。
と本書では述べられています。
チャンキング、チャンク化とは、メッシのように試合の流れを把握し、無駄な体力を使わずにすむように数多くの関連した情報をひとつのパターンにまとめ、それを蓄積、参照することで、意思決定のプロセスを簡略化し、瞬時に最も無駄のない動きを可能とする能力、言い換えれば優れた予測能力です。

「ゆっくりすればスムーズで、スムーズにいけば速くなる(Slow is smooth and smooth is fast)」――この言葉は、アメリカのSEALSを含め特殊部隊工作員全員の頭に叩き込まれている。
そう指摘するのが、元海軍SEALSの心理学担当主任エリック・ポッテラット博士です。
このチャンキングに必要なものこそ、場数であり、ベテランと呼ばれる選手が若者と同等にプレーが出来るひとつの秘密でもあります。これはスポーツに限らず、すべての分野で言えます。経験とはつまりチャンキングである、と言っても過言ではありません。
歳を取っても効果を上げることができるおすすめトレーニング方法

さいごにより具体的なトレーニング方法をご紹介して終わりにしたいと思います。
それがポラリゼーション、日本語では二極化と呼ばれるトレーニング理論です。
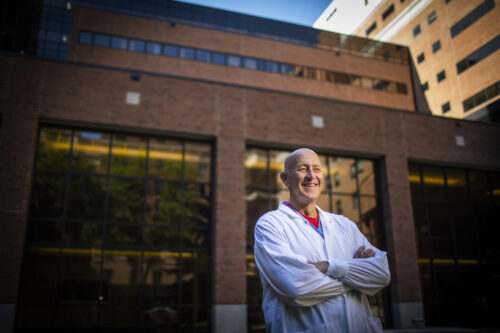
30歳を越えた年長ランナーや中年のランナーはどうやってスピードを保てばよいかと尋ねられて、メイヨー・クリニックの研究者マイケル・ジョイナーは、こう語っています。
「秘訣」が2つあります。インターバルをとることによって最大酸素摂取量をキープすることと、怪我をしないことです。

では具体的には何をすれば良いのか?
その回答として秘密のトレーニング理論、ポラリゼーションが紹介されています。
本書ではこう書かれています。
理由不明の停滞期を打破できると豪語されているこのポラリゼーション。
二極化という言葉の通り、トレーニングを超ゆっくりペースと高強度ペースを完全に二つに分けます。具体的にはトレーニング全体を超ゆっくりペース80%に対して、残り20%を高強度で行います。

この二極化の本質は2つのタイプの筋線維、速筋と遅筋を活性化させることにあります。
研究では、トレーニングを二極化させることで、インターバルトレーニング、すなわち乳酸性閾値のトレーニングだけに特化したトレーニングプランよりも、最大酸素摂取量、パワー、そして持久力、すべてを向上できることが示されました。
このポラリゼーションでのキモは運動強度、つまりしんどさです。
特に高強度トレーニングでの運動負荷。
2014年の研究では、太りすぎの成人が、週に3回、高強度のサイクリングを1分間しました。その結果、心肺機能が12%向上し、血圧が著しく下がりました。
そして重要なのがこの、高強度のサイクリングの「高強度」という指標です。

この研究で明らかになったことは、最大酸素摂取量が81%以上が必要であり、それ以下だと効果はガクッと減るということです。
つまりかなりハードなトレーニングが要求されるということです。すくなくともポラリゼーションにおいてもこの最大酸素摂取量81%以上を狙う必要があるのです。
実際の最大酸素摂取量と運動強度の簡単な測定方法
↓最大酸素摂取量(VO2MAX)と最大心拍数の目安を簡単に測れるサイト↓

※数値はあくまで目安です※

たとえば、30歳、安静時心拍数50の場合
VO2max 56.1=最大心拍数187
この【最大心拍数】に0.81をかけることで【高強度】の運動負荷がわかります。
最大心拍数187×0.81=151.47
つまり、トレーニング中に【151bpm(拍/分)以上】の心拍数をキープすれば【高強度】と呼べます。
計算がめんどくさい場合は自動的に計算してくれるランニング腕時計がおすすめです!
そして、トレーニングボリューム全体の80%を占める超ゆっくりペースも重要であり、この本ではこう表現されています。
もし、その「ゆっくり練習する日々」が、少し違和感を感じるほどにまでゆっくりでないならば、それは十分にゆっくりしていることにはならないだろう
このようにメリハリの極地にあるのがポラリゼーション、二極化というトレーニング理論です。もし停滞期に陥っているランナーや怪我が治らないランナーは一度試す価値があるかもしれません。
ラインナップ40万冊以上
無料キャンペーン実施中。いつでも退会可能。返品・交換も可能。
まとめ
まとめとして、歳をとっても第一線で活躍し続けられる、その理由としては、
まずはトレーニングの簡略化・効率化。メンテナンスプラクティスと呼ばれる効率的なトレーニングが可能となり、他の時間をほかの技能を磨くことに費やせます。
次に、タンパク質とゼラチンです。
このふたつを摂取することで、より長い間、パフォーマンスを落とさずに競技に打ち込める可能性が示唆されています。
さいごに、チャンキング。これは試合や相手の動きを予測できる能力のことで、目の前の情報をひとつにまとめ、頭の中でそれと類似した状況を思い起こすことで、意思決定のプロセスをショートカットすることです。こうすることで、怪我につながるハードな動きを減らしスタミナを温存できます。

これらが歳をとっても活躍し続けられる選手の秘密です。
今回はあくまで面白いと思ったトピックを簡単にまとめただけなので、かなり省略しています。少しでも気になった方は是非、本書をお取り下さい。
【うつ病も治る!?】有酸素運動と高心拍トレーニングはなぜおすすめなのか?
















































コメント