
みなさんどうも、こんにちは!
僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。

みなさんはこんな疑問を持っていないでしょうか?
運動をやめたらどれくらいの期間、能力は維持されるのか?どうすれば効果的にケガを予防できるのか?

もしくはこう聞くとどう思うでしょうか?
レース中に足が攣るのは実はナトリウムやカリウムなどの電解質不足のせいではない。風邪を引いたときこそ実は運動するほうが良い

どうでしょうか?えっ、と思わないでしょうか?

常識だと思っていたことが実は非常識だった?
今回はそんな視点で、元カナダ、ナショナルチームのメンバーでありケンブリッジ大学で博士号を取得した秀才アスリート。現在は科学ジャーナリストであるアレックス・ハッチンソンが書いたこの本。

良いトレーニング無駄なトレーニング、科学が教える新常識から改めて伝えたくなった5つのトピックを解説していきます。
このブログを最後まで見れば、科学に裏打ちされた正しいトレーニングがわかる。是非最後までご覧ください。
目次
良いトレーニング無駄なトレーニング、科学が教える新常識①

ケガをしてしまった。。忙しくてトレーニング出来ない。。
そんなランナーも多いと思います。
現在、わかっていることとしては、持久力は運動をしなくても約2週間は維持できますが、4週間以上経過すると、運動を始める前の状態に限りなく近づくということです。とくに、運動を始めて間もない人の場合、この低下は速くなります。逆に長期間にわたって運動をしてきた人は、数か月にわたって持続します。

東京大学の研究では、三ヵ月の集中的なトレーニングをおこなった被験者の筋肉は、一ヵ月の休養後にトレーニング開始前の状態に戻りました。ただし、トレーニングによって向上した神経筋は数か月間維持されました。

またデンマークの研究では、運動量を減らしてから2~3週間後に、インスリン感受性と脂肪の燃焼能力が減少しはじめると報告されています。
これらの研究から、人にもよりますが、デッドラインは長くて約3週間。3週間は何のトレーニングをしてなくても、比較的すぐに復活出来る可能性が高い。これが科学の答えです。

だからこそ無理をしてトレーニングする必要はありません。安心して休みましょう。
良いトレーニング無駄なトレーニング、科学が教える新常識②
ランナー最大の敵。それはケガ。その中でも本気で走っている人に多いケガのひとつが疲労骨折。
研究者たちの答えはふたつ。

ひとつめは歩幅を短くして回転数を上げることです。

アイオワ州立大学の研究では歩幅を変えることによる骨の損傷・回復効果を推測しました。その結果、歩幅を10%短くすると、疲労骨折のリスクを3~6%減らせることがわかりました。この結果から歩幅を短くして回転を速くすれば、疲労骨折のリスクを減らせる可能性があることが示唆されました。
この考え方は日本の運動生理学者、田中宏暁(たなかひろあき)名誉教授がこの本でも説明してるフォアフット走法でも同じ指摘をしています。
【徹底解説】ランニングする前に読む本 マラソンの科学的トレーニングとは?
では、疲労骨折のリスクを減らすふたつめの方法。それがふくらはぎを鍛えることです。

みなさんはメカノスタット理論というものを聞いたことがあるでしょうか?
このメカノスタット理論は比較的新しい理論であり、「筋肉によって骨の強度を促す圧力が与えられる」という考えに基づいています。
簡単に言うと、筋肉が増えると骨の強度の維持にも役立つということです。つまり骨の強度を上げるには筋肉を鍛えることが重要ということです。

だからこそリハビリには筋力強化が必須なのです。

Minneapolis, United States – July 23, 2012: Northrop Auditorium on the campus of the University of Minnesota. The University of Minnesota is a university in Minneapolis and St. Paul, MN and the 6th largest univerity in the USA.
ミネソタ大学による研究では、39人の女性ランナー(このうち半数は疲労骨折の経験あり)を対象に、骨と筋肉の大きさ、構造、密度を測定したところ、疲労骨折したことのあるグループはすねの骨が7~8%小さく、9~10%弱いという結果が出ました。
そして面白いことに、そうした骨の数値の違いは、ふくらはぎの筋肉の大きさに比例していました。また驚くべきことに疲労骨折した経験の有無と骨密度には関連が見られませんでした。
この結果から、彼女たちはカルシウム不足ではなく、骨が弱かった原因は、足の筋肉が不足していたことが示唆されたのです。だからこそ、メカノスタット理論。ふくらはぎの筋力強化で疲労骨折のリスクを減らせる可能性が高いのです。

カーフレイズなどの筋トレが重要な理由は実はここにあるのです。
では次に行きましょう。
良いトレーニング無駄なトレーニング、科学が教える新常識③
レース中にいきなり痛み出す足。故障ではなく強烈な痛み。そう足の攣り。
足が攣らないためと謳うサプリメントも多く出ており、それらの説明はこうです。

はたして本当にそうなのでしょうか?

この問題にケープタウン大学の運動生理学者マーティン・シュルナスはこう問いかけました。
もしそれが脱水症のような全身性の問題ならば、なぜ全身が痙攣を起こさないのか?
考えてみてください。もし体内の電解質のバランスが崩れるのなら、レースの後半になれば全身が攣るはずです。しかし、多くは足だけです。
この答え。足が攣るのは電解質のバランスが崩れるというより、収縮を誘発する興奮性入力と、弛緩を誘発する抑制性入力のアンバランスによって起こるという仮説です。
だからこそ、トレーニング不足のランナーがレース後半に足が攣りやすいのは、電解質うんぬんより、筋肉の耐性がついていないから。そうです。元も子もない話ですが、足の攣りを防ぎたければ距離走が必要なのです。
そうなのです。それについてシュルナスが行った研究であきらかになった2つのこと。
二つ目は痙攣を起こした人がレース直前の週にハードな練習をおこない、筋肉損傷と関係する酵素の血中濃度を高めていた傾向があるということ。
だからこそ、足が攣ってしまうと悩むランナーへのシュルナスのアドバイスはこうです。
十分にトレーニングし、現実的なゴールを設定し、レース前にしっかりと休養をとること。これだけで、痙攣を完全に防ぐことはできないにしても、その発生リスクを減らせます。

足が攣るくせがある人は是非、この点を考えトレーニングメニューを組みましょう。
では次のトピックです。
良いトレーニング無駄なトレーニング、科学が教える新常識④
当たり前ですよね。しかし、なんとなんと体調が少し悪いときは運動をしたほうがいい。これがまさかの科学的な答えなのです。

いったいどういうことなのか?

アメリカのホール州立大学トーマス・ワイドナーが携わったふたつの研究。
それがあえて風邪を引いてもらってパフォーマンスを調べるという前代未聞の研究です。
ひとつめの研究。それは45人の被験者にウイルスを注入し、風邪を引いた状態で、トレッドミルを走ってもらいました。
なんとランニングの成績や肺機能など生理反応のどれをとっても、両グループに違いは見られなかったのです。つまり、風邪を引いてもアスリートとしてのパフォーマンスが低下するわけではないのです。
そして二つ目の研究。これも同じように被験者50人に風邪をひいてもらい、半数は何もせずに安静にしてもらいます。
一方もう半数は最大心拍数の70%での運動を1日おきに40分間おこなってもらいました。
なんと両グループの症状の重さと継続時間には差が見出せず、意外にも運動をしたグループのほうが安静にしていたグループよりも少しだけ気分がよくなったと報告されました。
そうなのです。これらの研究から、風邪を引いた場合は運動をした方が良い可能性が示唆されたのです。
実際に風邪を引いているときの軽い運動が気分を若干よくするというワイドナーの発見を裏付ける事例はたくさんあると著者は指摘しています。

もちろん、だからと言って高熱で運動することはおすすめできません。
だからこそ、ワイドナーは「首チェック」というルールを提案しています。
それは、体調不良が首から上の症状(くしゃみや鼻水やのどの痛みなど)なら運動してもよく、首から下の症状(発熱や筋肉痛など)なら様子を見たほうがいいというものです。
良いトレーニング無駄なトレーニング、科学が教える新常識⑤

さて、みんさんはこんな事実をご存じでしょうか?
なんと2004年まで、世界アンチドーピング機構(WADA)はある物質を規制対象にしていたという事実を。
そう、ある物質とはカフェインです。

しかし、ご存じの通り、現在は合法です。

この出来事からカフェインはそこまで効き目がないかのように思われがちですが、その分野の第一人者であるカナダのゲルフ大学教授、テリー・グラハム博士はこう言っています。
カフェインは、一般的に認識あれているような効果の低いドーピング物質ではないと思います。他の物質以上にさまざまな効能があると考えられているのです。
実際に長年の研究から、カフェインは精神の働きを助け、摂取してから2時間は持久力が向上することが確証されています。さらにウエイトリフティングのような運動にも役立つこともわかってきました。

しかし、カフェインと聞くとこのようなデメリットを思い浮かべる人も多いかと思います。
それは利尿作用です。カフェインを取ると水分が体から出ていき、脱水症状の原因となり、持久系の競技ではパフォーマンスに支障が出るという反論です。しかし先ほどのテリー・グラハム博士はこうした意見を完全に否定しています。
さらに、カフェインと聞くと良く耳にするこの常識。カフェインを摂ると、体内の脂肪燃焼効率があがりパフォーマンスが上がるというもの。しかし、先ほどのテリー・グラハム博士によれば、この説が間違っていることも立証されています。

ではなぜ、カフェインを摂るとパフォーマンスの向上につながるのか?

現在、有力なのは、カフェインが筋繊維の収縮に細胞レベルで直接影響しており、神経系から信号が送られると筋繊維がより緊密に収縮するようになるという仮説です。
グラハム博士は、錠剤のカフェインとコーヒーとで効果を細かく比較しましたが、意外にも、カフェインの血中濃度が等しい場合、純粋にカフェインだけのほうがパフォーマンスの向上が見られることがわかりました。
コーヒーにはカフェインだけでなく、生物活性原料が含まれているため、それらの物質が複雑に作用し合い、パフォーマンスの違いが表れたと考察されています。
このように、カフェインはパフォーマンスアップを謳うサプリメントよりよっぽど確かな効果を得られる可能性が高いのです。まさに合法ドーピングなのです。
利尿作用も考慮して、「後半のここぞ!」という時に戦術として投入すれば自己ベストの更新が達成できる可能性は高まります。これが科学の答えです。
おすすめのカフェイン入りの補給食やカフェイン入り錠剤
※カフェイン入り錠剤はサプリメントではなく分類上は医薬品です(←これがキモです。くわしくはこの記事を読んでみてください!【徹底解説】サプリメントvs医薬品 効果的に速く強くなる方法)※
以上5つのトピック。
・どうすれば効果的にケガを予防できるのか?
・レース中に足が攣る本当の原因
・風邪を引いたときこそ実は運動するほうが良い
・カフェインの驚くべき効果
特に面白かったと感じたトレーニングに関する常識、非常識をまとめてみました。少しでも気になった方は是非、本書をお取り下さい。
ラインナップ40万冊以上
無料キャンペーン実施中。いつでも退会可能。返品・交換も可能。
【ランニングの専門家が考えられない】つま先着地VSかかと着地

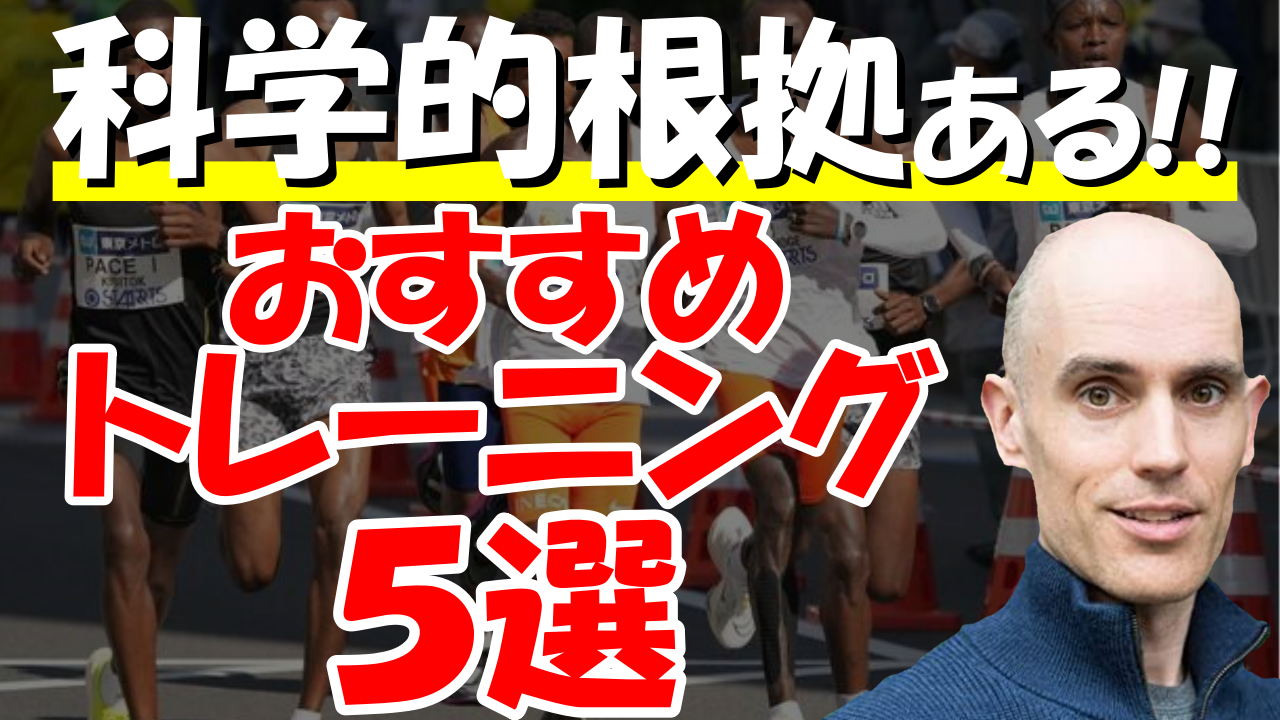







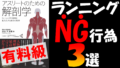
コメント