
みなさんどうも、こんにちは!
僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。
運動中はこまめな水分補給が大切!喉が渇く前に水分補給をしよう!
が、しかし、ここにひとつだけ大きくいびつな落とし穴が存在します。そしてそれはおそらく今後も表には出て来ないであろうそんな水分補給に関する闇深い落とし穴。よって、今回は水分補給とは一体何か?という当たり前すぎて考えてこなかった前提を、書籍や論文から紐解いていきたいと思います。

正直、今回はかなり切り込むつもりです。

なぜなら命に関わるから。
今からお話するのは、ある意味触れてはいけないタブーであり、現代の闇の部分。みなさんの常識がどのように作られ、何が正しく?何が間違っているのか?

YouTubeの動画をはじめ、タイトルやサムネについて批判する方がいらっしゃるので補足します。
このタイトルはすべて死ぬほど考えた上での戦略です。炎上までは言いませんが、現在の僕の発信力ではこの命に関わる情報を広めることはできません。知るか知らないかで助かる命があるのなら、僕は命を助ける方が正しい行いだと思います。

以下でも説明しますが、金儲けのための情報操作ではなく、命を救うための情報操作です。批判する方はその本質を理解していただければ幸いです。
目次
【熱中症と水分補給の神話】運動関連性低ナトリウム血症
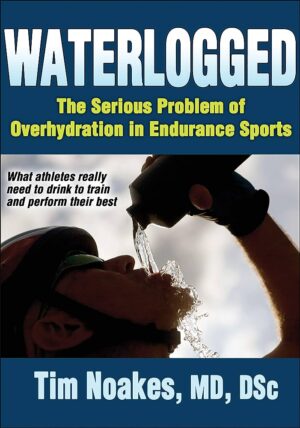
ここに一冊の本があります。それがこの本。
Waterlogged: The Serious Problem of Overhydration in Endurance Sports
日本語に訳すと「水浸し:持久系スポーツにおける過剰な水分補給での深刻な問題」と題された本です。

ちなみにこの本の日本語版は出ていません。

この本の著者こそ、スポーツ科学者、ランニング研究者の中である意味ぶっ飛んだ有名人。ケープタウン大学運動科学部およびスポーツ医学部名誉教授、ティム・ノークス博士。

↓このノークス博士に関しては様々な専門家が絶賛するこちらのスポーツ科学の名著を読むと、その人柄がわかります↓
限界は何が決めるのか? 持久系アスリートのための耐久力の科学
実際に癖の強さと言葉の強さで有名なノークス博士ですが、研究者としては優秀であり、2014年には「スポーツ生理学に素晴らしい貢献を果たした」として、名誉ある勲章も授与されています。
そんな彼が切り開いた分野のひとつこそ、運動関連性低ナトリウム血症(Exercise-Associated Hyponatremia)と呼ばれる命に関わる重大な現象の解明です。
↓ノークス博士のおすすめ研究↓


この言葉はおそらくほとんどの人が聞いたことのない専門用語だと思います。

これはスポーツ医学を学んでいない医者も含めてです。

それも当たり前でこの病態は比較的最近になって登場したある意味新しい病気だからです。
そして、この病気こそ、何を隠そう冒頭での本、「水浸し:Waterlogged」を説明するものであり、水分補給こそが命を奪う可能性を明らかにしたものなのです。
結論を言うと、マラソンやトライアスロンなど長時間の運動中に過剰に水分補給をすると最悪、死にます。後ほど、熱中症との危険性を比較しますが、結論から言って、この運動関連性低ナトリウム血症のほうが熱中症に比べて数倍ヤバいです。
そしてこの死に至る「運動関連性低ナトリウム血症」はみなさんのあの常識。
こまめな水分補給が大切!「喉が渇く前に水分補給をしよう!

これらの常識によって生み出されたと聞くとどう思うでしょうか?
【オックスフォード大学】スポーツドリンクのエビデンスは有効ではない【熱中症対策】

Tom Quad at Oxford University in a sunny day
2012年、オックスフォード大学EBMセンターのカール・ヘネガン博士らは医学雑誌BMJ(ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル)にこのような報告をしました。
科学的根拠に照らしてみれば、スポーツドリンクに関する過去40年間の研究は、有効な結果を示しているとは言えない。
さらにヘネガン博士らはスポーツドリンクに関するエビデンスを可能な限り集めて分析し、不十分な研究結果が確固たる証拠として扱われていたケースが多いことを明らかにしました。
顕著だったのは研究規模の小ささです。これが何を意味しているかというと「小規模研究では、介入が有効だという結果が出やすい」という事実です。
ヘネガン博士らが分析した研究106件のうち、被験者が100人以上だったのは1件のみ。二番目に大きかった研究でも53人で、平均は9人というのが判明したのです。
さらにこんな事実も発見されました。それは統計上の操作です。たとえば、ある研究ではセグメントを一つ分析対象から除外することによって、炭水化物入りのドリンクのメリットを3%から33%に増加させていたりしたのです。
オックスフォード大学IBMセンターのカールヘネガン博士らの研究
『Forty years of sports performance research and little insight gained』

社会にメスを入れる素晴らしい論文。ちなみにBMJ専門ポッドキャストチャンネルで毎週発行される抄録を聞けるらしい。これを聞き流している研究者や医者がいたら、恐らく変態!
これらの研究の上で声高に叫ばれているのが、現在の常識、「運動中はこまめな水分補給が大切」「喉が渇く前に水分補給をしよう」です。

そうです。アクエリアスやポカリスエットなどスポーツ飲料を売る営利企業です。
よって、研究者たちはこう指摘します。
実際には、これは科学というよりもマーケティングなのです。
ここまで聞くと、いろいろと反論したい研究者や利害関係者がいると思うので、より深ぼります。
まずは、実際の論文を見てください。これは日本語なので、誰でも読めるはずです。
ここにはこう記されています。
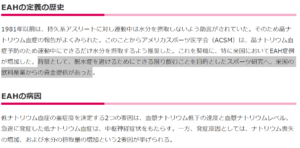
背景として、脱水症を避けるためにできる限り飲むことを目的としたスポーツ研究へ、米国の飲料産業からの資金提供があった。
この飲料産業とは現在、日本から撤退した世界一位のスポーツドリンクメーカー、ゲータレードだと思われます。

実際の論文は概要欄に貼っておくので、是非、ご自身の目で一次情報にあたって確認してみてください。
運動関連低ナトリウム血症(EAH)のリスクと予防に関するナラティブレビュー(日本栄養スポーツ協会)

この一本でOKと言っても過言ではない運動関連性低ナトリウム血症の全体像をとても良い感じにまとめている日本語の論文。いろいろな利害関係が発生しているためより信頼性のある手法(メタ解析など)で深ぼるのは難しい!?知らんけど。
↓日本栄養スポーツ協会ははっきり言って、神!↓

というような事情で、スポーツドリンクの有効性を高めるエビデンスがマーケティングに繋がるために、恣意的に情報をコントロールしたり、有効性を高めるあまり好ましくない手法があえてとられた可能性を否定できないのです。
実際問題、米国スポーツ医学会、米国ストレングス&コンディショニング協会、米国アスレティックトレーナーズ協会など大手の団体はスポーツドリンクメーカーからの資金提供を受けています。
また、日本においてもスポーツ科学基金はアクエリアス基金という名前です。ちなみにこれはアクエリアス、コカ・コーラ社がこれらの研究に介入しているということではなく、あくまで金銭的なサポーターであるという事実だけを僕は言いたいだけですので、くえぐれもそ曲解しないでください。
スポーツ科学基金(アクエリアス基金)

営利企業が悪いわけではない!今回は恣意的に悪い側面のみを切り取ったので、補足します。これらの営利企業がお金を出すことで、特定の研究や特定の分野がブーストされ、新発見に繋がったり、研究者等現場にいる方が正当な報酬を得られることは大きなメリットだと僕は考えます。全ての事象には良い面と悪い面が必ずあります。そのようなマクロな視点で情報にあたりましょう!鵜呑みはダメ絶対!
このように営利企業がバックにいて、関係者にお金を出して自身や自社の利益を最大化する。この文脈ではやや的が外れているかもしれませんが、このような行為を医療の分野で「病気喧伝」と呼びます。

この行為は特集が組まれるレベルで問題になっています。
↓詳しく実際の事例と関連論文を貼っておきます↓
ハーバード大学が企業から資金を受けていた問題(日本語記事)
病気喧伝(Disease Mongering)の特集論文
これ一本でOK的な有名な論文
よって本質的に言えば、営利企業との共同開発や営利企業がお金を出して行った研究などは「そもそも中立なのか?」という結構闇深く難しい事態が発生しています。官民一体の研究が多い現状なので特に。
「世界一走りたくなるワンステップ科学から紐解くランニング」
※売上はこの本の編集や校正に携わって頂いた協力者様に分配されます※
「介護や病気など様々な理由で在宅でか仕事が出来ない協力者様」のためにこの本を出版します。歩合制なので、面白いと思えば実際に書籍を買って頂ければ幸いです。
↓キンドルアンリミテッド会員なら「無料」でスマホ・タブレットからも読めます↓
【30日間無料体験】読み放題サービス キンドルアンリミテッド
↓私の思い↓

少し脇にそれますが、知っていて損はないのでひとつこれらの問題に関連する有益な情報をご紹介します。それがコクランレビューです。
まずはコクランにあたれ!
科学的根拠を重視する医療関係者なら一度は耳にしたことがあるコクランレビュー。コクランレビューとは営利企業や特定の団体から資金を受けていない「中立」を謳うNPOが運営している信頼性が高い研究データベースです。

日本語版もあり、英語がわからない人でもアクセスできます。

内容はバリバリ医療系ですが、僕はプロテインやサプリメントを含め調べものはまずはこのコクランから調べたりします。
コクランレビュー(日本語版)

英語版もおすすめ。中立は正義
水分損失で本当にパフォーマンスは低下するのか?

と、ここまでいろいろ言ってきましたが、「水分がわずかでも不足すれば健康上のリスクが生じ、パフォーマンスとリカバリーを妨げる」というのはある意味事実です。
だからこそ初期の研究者は「善意」でこれらの事実から水分補給を推奨しました。結果、そのことに目をつけた営利企業が販売促進事業の一環としてガンガン研究に投資をしてマーケティング戦略として水分補給の重要性を声高に主張した。が、その戦略にによってつくられた常識によって、過剰な水分補給が促され実際に命を落とすランナーが現れたというのが大まかな流れです。

この事態を受けて、スポーツ科学者として著名なグラスゴー大学のヤニス・ピツラディス博士らは、
フルマラソンを走る際、喉の渇きに従った水分補給が、失った水分量をすべて補う方法よりも劣ることを示すエビデンスはないようだ。
と述べ、マラソンやウルトラマラソン、アイアンマントライアスロンなどでは、レースでもっとも体重を失った選手が優勝するケースが多いとも報告しています。
先程のスポーツ科学の名著でもこのように指摘されています。
マラソンランナーが運動機能に障害が出るレベルの脱水症を起こしながら世界記録を樹立した。
これらの事実はスポーツドリンクメーカーの主張とは違い、水分損失とパフォーマンスには密接な関係がないことを示唆しています。つまり水分損失には、パフォーマンスに影響を及ぼさない許容範囲があると考えられるのです。むしろ、おそらくは体重が軽くなったことによる負荷の軽減のために、ある程度の水分損失にはパフォーマンスを向上させる可能性があることすら示唆されています。ですから、水分補給を深ぼっている名著(GOOD TO GO)にはパフォーマンスのために、
体温と水分損失に注目するのはおそらく正しい戦略とは言えない
とまで述べられています。
第二章がまるまる水分補給に関するトピック。ここからかなり引用しました。第一章で読むのを諦めたらダメ笑。第二章から盛り返す名著。出典も充実しておりこの一冊からかなり深ぼれるはず。あまり知られていない本ですが、本当におすすめ!
マラソン中の水分の摂りすぎで起こる運動関連性低ナトリウム血症とはどんな病態?

ではこのレース中の水分の取りすぎ問題。運動関連性低ナトリウム血症とはどのような現象なのか軽く見ていきます。この病態は一般的には水中毒と呼ばれるものです。

水分の過剰な取りすぎで何が起こるのか?
それは細胞の膨張です。大量の水分が細胞に入ってくることで、細胞がパンパンにふくらみます。結果、それが脳に起こるとそこでThe Endつまり、死に至ります。そしてこの運動関連性低ナトリウム血症の厄介なところは初期症状がなかったり、あったとしても脱水症状のそれとよく似ていることなのです。

つまり、脱力感、頭痛、吐き気、めまい、立ちくらみなど。
だからこそ、運動関連性低ナトリウム血症を脱水症と誤認してしまうことで、実際どうなるか。
2002年のボストンマラソンでは、ハーバード大学医学部の研究者がレース後にランナー488人の血液サンプルを採取した結果、13%のランナーが低ナトリウム血症と診断可能な状態にあり、3人が重篤な状態に陥っていました。そして悲しいかな、このレースで28歳のシンシア・ルセロという女性ランナーが重度の低ナトリウム血症で亡くなっています。
↓2002年にハーバード大学の研究者らが行ったボストンマラソンでの研究↓
『Hyponatremia among runners in the Boston Marathon』
また、ドイツの研究でも、アイアンマントライアスロンヨーロッパ選手権に出場した千人以上のトライアスリートの血液サンプルを採取した結果、10.6%が低ナトリウム血症になっていました。
↓アイアンマントライアスロンヨーロッパ選手権で行われた研究↓
『Hyponatremia among Triathletes in the Ironman European Championship』
そうなのです。運動関連性低ナトリウム血症の知識がないとパフォーマンス低下と脱水症を結びつけ、より水分を摂ってしまうという悪循環が発生してしまう可能性があるのです。

これが「こまめな水分補給は大切」「喉が渇く前に水分補給を」というアドバイスが招く悲劇です。

とは言っても、水分を補給せずに熱中症になればそれこそ致命的になるのではと思う方も多いと思います。
熱中症の本質とは?

ではこんな研究をご紹介します。
それが、アメリカ陸軍省環境医学研究所の生理学者サミュエル・チェウブロント博士の研究です。
彼は
水分損失は熱中症の必須条件ではない
と主張し、
運動時の熱中症は、暑い環境(または寒い環境でも)ハードな運動をすると、通常、発汗によって大量の水分が失われる前に起こる
と指摘しています。
↓アメリカ陸軍の生理学者、サミュエル・チェウブロント博士の研究↓
A Case Report of Idiosyncratic Hyperthermia and Review of U.S. Army Heat Stroke Hospitalizations

感染症が熱中症において重大なリスクファクターのよう。体調がすぐれないときにトレーニングすると熱中症の重症化リスク↑
実際に20年に及ぶ軍の熱中症のデータを解析した結果、水分損失が関連していた割合は20%しかありませんでした。
大半のケースでは、水分損失は熱中症の原因になっていないか、まったくの無関係だった
と結論づけています。
よって、「水分損失量は熱中症と関連性はあるが本質的ではない」と博士は主張しています。
と聞くと、「そんなはずはない。体の水分がなくなって熱中症になるのだから」と言いたくなると思います。

そこが盲点。いや、マーケティングと言われる由縁なのです。

みなさんは熱中症の本質をご存じでしょうか?
熱中症をかなりかみ砕いて説明すると、体温が上がりすぎて、体中の細胞がぐつぐつと煮えたぎった状態になり、それによって内臓が機能を停止し、多臓器不全というかたちで意識不明、最悪死に至ります。
↓熱中症(慶応義塾大学病院)↓
熱中症を解説しているサイトで一番有益。ここに本質あり!
問題なのは体温の上昇なのです。だからこそ、熱中症になれば、まずは体を冷やすことが求められます。そう、日陰に連れていき、わきの下や鼠径部など大きな血管が通っている場所を氷などで冷やす。

このような知識はみなさんも持っていると思います。
マーケティング戦略としての熱中症対策

では、よくよく考えてください。水分の損失は体温上昇とどれほどまでに関連しているのでしょうか?
確かに関連はしています。がしかし、関連しているだけなのです。そう、何が言いたいのかと言うと、水分損失と熱中症は相関関係でしかないのです。

因果関係ではない。これが重要です。
スポーツ飲料メーカーが行ったこと。それは熱中症と水分補給を因果関係で結んだことにあります。売上を上げるためのマーケティング戦略の一環として。
よって、さきほどのアメリカ陸軍の生理学者、サミュエル・チェウブロント博士の指摘。
大半のケースでは、水分損失は熱中症の原因になっていないか、まったくの無関係だった。
事実、人間は水分をほとんど摂らずとも活動できることが人類学者のフィールドワークで明らかになっています。水分調整に関するホルモンバソプレシンから紐解く持久力のひみつはこちらをご覧ください。
【ランニング初心者がマラソンを完走した方法】科学が教えるトレイルラン、低炭水化物食、マインドフルネス
【熱中症の重症化リスク】夏風邪や薬の影響


あとひとつ付け加えるとするなら、起こった現象をそのまま捉えると重要な因子を見落とすということです。
どういうことかと言うと、薬によって上手く体温を下げることが出来ない状況が発生するのです。よって、水分補給うんぬんの前に服薬状況をまずは確認すべきだと僕は考えます。

もし、ADHDやうつ病など神経伝達物質に影響を与える薬を飲んでいる場合は絶対に注意してください。
ツールドフランスで亡くなったサイクリストの事例
1967年、ツールドフランスにおいてイギリス人サイクリストのトム・シンプソンが熱中症で亡くなった。この悲劇の主な原因は「アンフェタミン」という薬によるもの。この薬は体温を調節する機能にも影響を与え、深部体温が下がらない。また、このアンフェタミンはADHDやうつ病の患者によく処方されており、実際にアメリカではこの種の薬の影響のために体温を下げられず死亡したケースにおいて、当時、指導にあたっていたコーチが「無罪」になっています。死亡した子どもがADHDの薬を服用していたのが(主な)原因。よって、神経伝達物質に影響を与える薬を服薬している場合は要注意。さらに上記の慶応病院の熱中症のサイトでも、「乳幼児、高齢者、視床下部に作用する薬物を内服している場合には熱中症となりやすく、注意が必要です」と記載あり。

ランニング指導者は以下の書籍「限界は何が決めるのか?p205~」を必読。ここに詳細が載っています!
体温に関するトピックで熱中症についての記述あり。アスリートの限界のひとつは温度(体温)!出典がついていないのだけが死ぬほど残念。出典がないため不明確ですが、おそらく上記のGood to Goと同じ研究が引かれていたり、【アスリート×熱中症】の本質を知れる必読書。有名なランニング研究者の著作にはこの本が参考文献としてほぼ必ず載っていると言っても過言ではない本物の名著。ティム・ノークス博士(と彼の仮説)についても深ぼられています。サクッとは読めないですが、おすすめ!

少し脱線しましたが、話を戻してアラバマ大学バーミンガム校医学部教授で腎臓生理学の第一人者であるケリー・アン・ハインドマン博士はこう言っています。
人々は脱水症状になることを過剰に心配している。しかし実際には、水分の過剰摂取のほうがはるかに陥りやすい。人体には水分を保つための優れたメカニズムがある。ある程度の水分損失は悪くない。身体がそれに対処できるからだ。
さらにアスリートがよく耳にする「喉が渇く前に水分をとるべき」という通説に対してオークランド大学スポーツ科学部教授のタマラ・ヒュー・バトラー博士は
喉が渇く前から水分を摂る必要はない
とも指摘していたりします。
というのも、エネルギー代謝の仕組みをしっかりと理解していれば、なぜ経口での水分補給にそこまでこだわる必要がないのかも理解できると思います。

人体が持っている水分補給の裏技。とても賢い仕組み。
難しい話はおいて置いて、簡単に言うと、エネルギーを取り出す際に水が生まれるのです。実際にエネルギーの発電所とも言われるミトコンドリアは、吸い込んだ酸素を使って1日にコップ1杯よりも多いくらい(300ミリリットルほど)の水をつくっています。
ミトコンドリアの代謝(水)の話はp75~。電子伝達系で水が作られる!人体はおもろい!人体の面白さ、合理性が垣間見れる名著。

ちなみにこれは安静時の話。
運動するとより大量の酸素を取り込めるので、より多くの水分を作り出せます。これを再利用したりして、アフリカの砂漠に住む狩猟採集民であるサン民族は現代のランナーが30分ごとに飲むべきとされる量の水で、丸一日、灼熱の砂漠に近い環境を走りつづけられるのです。

そう、人間は、厳密なスケジュール通りに水やスポーツドリンクをがぶ飲みしなくても運動ができるように進化してきたのです。
砂漠の民のヤバい水分補給の逸話はp223~。「誇張しすぎだ!」と思わないでもない。本当か~?笑
余談ですが、同じハーバード大学の教授がこの本のくだりを大げさだと批判(指摘)していたりします。ある意味そこまで影響力がある本と言っても過言ではない!?
【アクアポリンを強化】最強の水分損失対策・マラソン中の熱中症対策
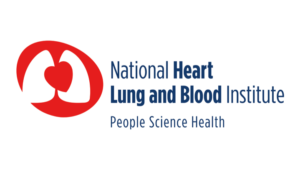
そしてその能力は強化できるのです。
米国立心肺血液研究所の責任者マーク・ネッパー博士は、
日頃から水分を多くとっていると、貴重な水分を保つための能力が衰える
と述べています。
体内に水分がたっぷりあると、水を調整する超重要なタンパク質である「アクアポリン」を活性化させる必要がありません。このような状態が続くと、アクアポリンは不要だと見なされ、その数が減っていくのです。

するとどうなるのか?
本当に必要になったときに、体内の水分量を適切に調整してくれるアクアポリンが足りないという状況に陥ってしまいます。
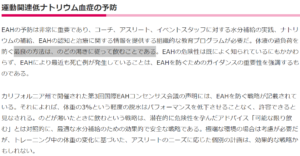
だからこそ、先程あげた論文にこうある通り、喉が渇いたときに水を飲むように心掛けるのです。そうすることで、アクアポリンを維持でき、アスリートは水分不足に対処しやすくなるとのこと。もっと言えば、熱中症にならない程度であえて喉の渇きを我慢することで、水分不足に対応するトレーニングができるとも言えます。
が、しかし、そんな水分不足も許容できない範囲が存在します。つまり、このラインを超えたらゲームオーバー。

それが体重の3%

ちなみにこの話の対象はあくまでマラソンランナーです。

では、さいごの一押しとしてカリフォルニア大学デービス校の自身もウルトラランナーであるマーティン・ホフマン博士の話を引用したいと思います。
彼はこう言っています。
喉の渇きに応じた水分補給と計画通りの水分補給を比較した研究をメタ解析した結果、喉の渇きに応じた水分補給がパフォーマンスを低下させるという現象は確認されなかった。
まとめ(僕が本当に伝えたいこと)

以上から水分補給にまつわる闇の部分と我々の体は実は水分を補給しなくても活動できるように上手く作られているということを専門家の話をベースに解説してきました。僕が言いたいのは、「だからこそ水分補給は不要!水分補給をするな!」という極論ではありません。
実際に最近もランニング中に熱中症で意識不明になったニュースなど、熱中症が恐ろしいのも事実です。よって、水分補給は大切ですし、僕自身、計画的に水分補給をするタイプです。

が、しかし、水分を摂りすぎると命に関わる可能性がある。

これだけは知っていてほしいのです。
知るか知らないかで最悪の自体が防げる。もしくはあなたの大切な人を守れるかもしれない。命を守るための知識。

これが僕が思う本当の知識です。
冒頭でも指摘しましたが、この真実はおそらく広がりません。というか積極的に宣伝されることはないと思われます。なぜなら、スポーツドリンクメーカーの売上が落ちるからです。事実これらの情報はかなり昔から明らかになっていますが、今でもスポーツにおいてこまめな水分補給の必要性や「喉が渇く前に水分補給をしよう」というキラーフレーズをよく耳にし、これらの命に関わる負の部分が全く耳に入ってこないことがその証拠です。
そして先程話したように、熱中症と水分損失は相関関係でした。が、しかしです。この運動関連性低ナトリウム血症と過剰な水分補給。これは「因果関係」なのです。

相関関係ではないというのが本当にヤバいことなのです。
そう、この運動関連性低ナトリウム血症は確実に数値として、因果関係で説明できる。よって、知らなかったでは済ませられない。
さいごに僕は自分の意見を押し付けたいわけではありませんし、これらの情報を全て鵜呑みにしろ!と言っているわけでもありません。是非、ご自身で実際の一次資料にあたったり、自分自身の頭を使って考えて欲しいだけです。その上で「水分補給をしまくる!」という意見でも全然構いません。

なぜなら、選択肢の中で自らが自発的に選んだことに価値があるからです。
知識というのはテストで点数をとったり、マウントをとったりするのではなく、誰かを助けたり、自分自身を助けるために使うべきだと僕は常々考えています。

出せるだけの資料はコメント付きで載せたので、是非、各自で深ぼってみてください。
【ジョギングやランニングはするな?】ハーバード大学教授がおすすめするマラソントレーニング方法












コメント