
みなさんどうも、こんにちは!
僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。
人間は、地球上で最も耐久力のあるランナーだ。そう、最強なのだ(p29)。

ユタ大学で自身もガッツリと山を走るトレイルランナーでもあるデイヴィッド・キャリアー博士が成し遂げたこと。
それは砂漠の中、二本の足で獲物を追いかけ続け、ヘロヘロにして捕まえるという人間しかできないであろう摩訶不思議な狩猟方法。その名も持久狩猟。
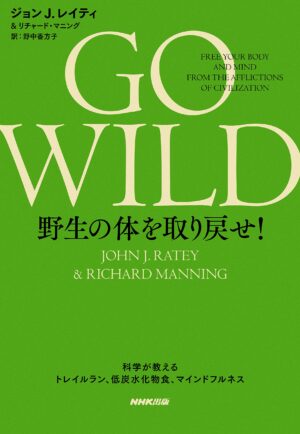
この成功の鍵について、この本ではこう指摘されています。
ユタ大学のデイヴィッド・キャリアーは持久狩猟で何度も失敗したが、アフリカのサン人など砂漠の民の助言を得て、みごとに成し遂げたのだ。成功の鍵は、走り方ではなく共感力だった。
人間のコミュニケーション能力がランニングという狩り方法と深く結びついているため、人類は走るように適応しただけでなく、走ることは人類の本質的な属性とされ、まさに人間こそ「走るために生まれたBorn To Run」と言われる起源となりました。
持久狩猟はこの本に詳細に載っています!胸アツ!必読です!ちなみに冒頭で取り上げたデイヴィッド・キャリアー博士やこの本に出てくる持久狩猟を広めたハーバード大学のダニエル・リーバーマン博士らの現在の主張は「人間は走るために生まれたのではなく、走るのは生き残るため(狩りをするため)の一つの手段でしかない」という考え方に落ち着いています。
↓くわしくはこちら↓

本日は運動と脳のスペシャリスト、ハーバード大学大学院ジョン・レイティ博士が書いたその名も「GOWILD野生の体を取り戻せ!科学が教えるトレイルラン、低炭水化物食、マインドフルネス」
この本からランニングやランニングにまつわる食事、はたまたメンタルの作り方を紐解いていきたいと思います。
この動画を最後まで見れば、ハーバード大学の准教授が教える新たなランニングの視点、切り口がわかり、ランニングにプラスとなる人体や脳に備わった超興味深い知識が手に入る。後半には驚くべき研究もご紹介します。

是非、最後の最後までご覧ください。
目次
【ウォーキングvsランニング】スピードの最適解

それは歩くスピードには最適解が存在するという事実です。
この本によれば「人間は、毎秒1.3メートルの速度で歩くとき、エネルギー効率が最高になる」と指摘されており、この毎秒1.3メートルとは時速約4.7km、1キロ約12分45秒程度のスピードです。これが最小のエネルギー消費で一定の距離を移動できる最適解。これはグラフにするとU字カーブを描きます。

が、しかし、ランニングはこのU字カーブではなく、平らな線。

これはつまり、ランニングにはエネルギー消費効率に関して最適となる速度がないことを意味しています。
それこそ個人差の影響が大きいからです。ランニングでのエネルギー効率はその人の体の状態や運動経験に左右されるとのこと。
このようなランニングでの大きな個人差は他の動物には見られず、ある意味ランニングこそが人間を象徴する活動であることの裏返しのような気もします。

ランニングという二本足での移動は一見簡単そうに見えて実は難しいというのが科学的な視点からうかがえるのです。
「世界一走りたくなるワンステップ科学から紐解くランニング」
※売上はこの本の編集や校正に携わって頂いた協力者様に分配されます※
「介護や病気など様々な理由で在宅でか仕事が出来ない協力者様」のためにこの本を出版します。歩合制なので、面白いと思えば実際に書籍を買って頂ければ幸いです。
↓キンドルアンリミテッド会員なら「無料」でスマホ・タブレットからも読めます↓
【30日間無料体験】読み放題サービス キンドルアンリミテッド
↓私の思い↓

マラソン完走(ランニング)に必須なバソプレシン

そしてこのランニングで鍵となるのが、この物質。
みんさんは最も古いホルモンをご存じでしょうか?
それがバソプレシンというホルモンです。
このバソプレシンの主な役割は体内の水分調整(や血圧調整)。なぜバソプレシンが最古のホルモンと言われるのか?その由縁こそが、全ての生命は海から誕生してきたことに起因します。
海から陸に上がるには水分を調整する必要があった。よって全ての生物が最初に獲得したのがこのバソプレシンによる水分調整機能。だからこそ、最古のホルモンと言われています。

先程のユタ大学のデヴィッド・キャリアー博士こそ、このバソプレシンの働きを追うことで、ランニングと人間を結びつけたのです。

いったいどういうことなのか?

※参考画像(この写真はサン人ではありません)※
それが砂漠で暮らすサン人という狩猟採集民族の存在です。
彼らサン人はなんと現代のランナーが30分ごとに飲むべきとされる量の水で、丸一日、灼熱の砂漠に近い環境を走りつづけられるのです。
この芸当を説明できるのが生物最古のホルモンであるバソプレシンの存在。
じつは、運動、とりわけ暑い日のランニングはバソプレシンの放出を促し、その働きによってランナーの体は水を外に逃がさなくなります。それが、
サン人が砂漠でうまくやっていける秘訣である
とこの本では指摘されています。
よって、ここで興味深い真実があきらかとなります。
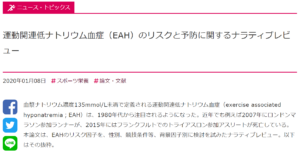
実は冬のマラソン大会での死因の大きなひとつが、なんと「水分の摂りすぎである」という衝撃的なデータの存在です。これは日本スポーツ栄養協会が出した超おすすめのめちゃくちゃ良い記事があるので、以下をご覧ください。
★マラソン大会での水分の摂りすぎで死ぬ理由(日本スポーツ栄養協会)★
運動関連低ナトリウム血症(EAH)のリスクと予防に関するナラティブレビュー

低ナトリウム血症という水分取りすぎで起こるヤバい事態。営利企業(明言されていませんが、ゲータレード)が自社の商品を売るためにガンガン金をツッコミ、水分補給の重要性を植えつけたために、水分の取りすぎで亡くなるという悲しい資本主義の背景がこの低ナトリウム血症には隠されています。ちなみに熱中症(水分不足)と低ナトリウム血症(水分過剰)では後者の方が圧倒的に「死亡率が高い」です。だからと言って、水分を取らないことを良しとしているわけではありません。水分補給は大切です!★補足★
このページを含め、このサイトの「論文・文献」をご覧ください!ここで知識を深めればそれだけでOK感はあります。本当に本当に素晴らしい!↓神サイト↓


補足しますが、僕は水分を摂る必要がない!ということを言っている訳ではありません。
水分が取れる環境なら摂った方が良い。彼らの芸当は生まれ育った環境が大きく関係しています。よって現代の僕たちの環境にはその環境に最適な方法論があり、それを上手く使うことがベストなのです。よって、サン人を真似て水分を摂らないという選択肢は熱中症などの最悪の状態を引き起こします。あくまで、人類の進化の設計上、実は水分なしでもかなり動けるという事実がDNAの中には隠されているというだけです。
また、これは僕が考えたおもしろ仮説ですが、このバソプレシンは鼻から吸引できるという特性があります。よって、炎天下での意図的なバソプレシン吸引での水分調整能力アップはありえるかもしれません。実際に同じような分子のオキシトシンの研究は数多く行われています。ちなみに先行研究等は一切調べていないので悪しからず。
なんとバソプレシンは神経伝達物質としても働きます!これが何を意味しているかと言うと、運動する「やる気」もバソプレシンが関係しているという衝撃の事実です!気になる方は以下の書籍p127~をご覧ください!「マジで!?おもしろ~」となり、生物最古のホルモン、バソプレシンの理解が深まります。ちなみにこのメカニズムが「超」面白いので、スポーツの専門家や(運動)生理学を学んでいる方は必読です!人体の合理性にはほれぼれします。
↓著者は信州大学医学部の研究者↓
【マラソン完走の極意】リチャード・マニングのトレーニング方法

そしてこの本で最も興味深いのが、著者のひとりである、リチャード・マニング。彼のマラソン完走の極意です。ちなみに彼は優秀なジャーナリストであり、数々の受賞歴もあるそんな人物。
彼がマラソンに挑戦する前の体重はなんと96キロ。しかも、うつ病の持病があり、心身ともに健康とは言い難い状態でした。
そんな彼がマラソンを完走し、体重も五ヵ月で11キロ落とし、結果的にうつ病も寛解というかなり良い状態にまで回復したそんなランニングの極意がこれです。
気持ちよく走れる距離を決め、徐々に延ばしていく。しかし、週に10%以上は増やさないこと。週に一度、長距離を時間をかけて走る。週に2日はまったく走らない日を設ける。そして三週間に一度は、まるまる一週間休む。この方法はとてもうまくいき、わたしはマラソンを完走することができた。
そしてトレーニングをはじめて五ヵ月で体重が84キロまで落ちました。

ここから彼はランニングのとりことなり、ウルトラマラソンやトレイルランニングを完走するまでになります。

が、しかし彼も壁にぶち当たります。
【非常識のランニング攻略法】トレイルランを完走できた驚くべき食事方法

それが2012年に開催された48キロを走破するトレイルランのレースです。
このレースでぶち当たった壁こそ、ハンガーノックというフラフラ状態。しかも2回も。彼はこう回想しています。
わたしがそうなったのは、栄養学の標準的なアドバイスに従って、用意されていた炭水化物とゼリー飲料を大量に摂取したからだ。
そして、なんとかボロボロになりながら完走。その苦い経験を踏まえ、この本の執筆のためにジョン・レイティ博士を含めさまざまな専門家の知見を持っていた彼は、このような結論にたどり着きます。
大昔の狩猟採集民は30分ごとにパウチ容器入りのコーンシロップを補給したりしなかった。
さらに、こう続けます。
このことについて考えた人はいるだろうか?
そして、その分野の専門家を見つけます。それがスティーヴ・フィニー博士とジェフ・ヴォレク博士です。
↓実はこの2人は以前こちらでも取り上げました↓
【2.5倍アップ】糖質制限ダイエットで脂肪燃焼効率を上げまくるとどうなるのか?【スーパーノヴァ実験と低糖質高脂質の食事】

それこそAIS、オーストラリア国立スポーツ研究所が行ったプロアスリートを脂肪燃焼マシンに変身させる画期的な実験、超新星爆発という名前をあたえられた「スーパーノヴァ」と呼ばれる実験です。この実験のもともとのきっかけとなった研究を行ったのが何を隠そうスティーヴ・フィニー博士とジェフ・ヴォレク博士の両研究者です。
↓両博士の話はこちらの本にも載っています↓
リチャード・マニングが見出したハンガーノックを克服する方法。それこそが食事法です。
一日の炭水化物の摂取量を約50グラムに制限。これは、リンゴ一個とカブ数個で限度いっぱいとなる量とのこと。が、しかし、乳製品は食べてOK。
この食事法により、脂肪の燃焼効率を上げ、炭水化物をセーブする体に作り変える。ケトジェニックダイエット、いわゆる糖質制限ダイエットです。

ここでこの本のタイトル回収です。

この本のサブタイトルを思い出してください。
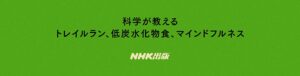
それこそ、低炭水化物食
この低炭水化物食に切り替えることで、高血糖と低血糖の間を行き来したりせず、長距離を完走でき、
今では、食べ物を一切摂らなくても7時間走れるようになった
と言っています。しかも4時間を超すレースでも壁にぶち当たることもなくなったとも。
マラソンやウルトラマラソンでの胃腸トラブルの防ぎ方

個人的にはマラソンやこのような「超」がつく長距離レース(ウルトラマラソン、トレイルランニング)での胃腸トラブルも食事を吸収する能力が低下することによってもたらされると仮定するのなら、極力食事を減らすという、まさかの方法論も考えられるのです。

もちろんあくまでひとつの選択肢としてです。

補足しますが、このケトジェニックによる脂肪燃焼マシン化は記録を狙うものではなく、完走を狙う、楽に長時間動き続けるという文脈においてです。
だからこそ彼はこう言ってます。
従来のスポーツ栄養学に照らせば非常識かもしれないが、それでうまくいっているし、何よりも手軽なのだ。
そしてこの非常識をガチガチのスポーツ栄養学のトップ研究者が扱った実験こそ何を隠そう「スーパーノヴァ」と名付けられた実験なのです。どのような結果になり、何がわかったのかはこちらで論文ベースで解説しています。
↓スポーツ栄養学のトップ研究者が行った画期的なケトジェニック実験↓
ランニング初心者にもおすすめ?瞑想の効果

では最後にマインドフルネス(瞑想)というやや胡散臭い言葉についてスポットライトを当てたいと思います。
この本ではこのように記されています。
年月を経て筆者は、この狩猟採集民の思考とほぼ同じものが現代人にも見られることに気づいた。それは「瞑想」だ。
ちなみに瞑想とはリラクゼーションや至福を得ることを目的として行うものではありません。この瞑想の目的が狩猟採集民の思考とほぼ同じと言われる由縁です。
それが、「今を生きること」です。
つまり、瞑想は「今、ここ、この瞬間」に注意や意識を向け続けることであり、それこそまさに野生の人々が自然環境で生き延びるメンタルと同じなのです。

よって著者は瞑想と狩猟採集民の思考をイコールで結んだのです。
あまりピンとこない方も多いと思うので、補足しておきます。
※狩猟採集民の生き方は「瞑想」と一緒!?※
いろいろな狩猟採集民に関する本を読むと彼ら彼女らの生き方は未来を考えていない、「現在に全振り」する生き方が特徴です。言語であっても未来を表す表現(will,be going toなどの未来形)がそもそも存在しない部族がいたりして興味深いです。よって、赤道近くに住み、一年を通して気候の変動が少ない部族では、食料の備蓄という概念すらあまりなく、「飢えたらどうしよう」みたいなことも考えてないらしいのです。過去でも未来でもなく、いかに今を精一杯に暮らすのかが最も重要。よって、瞑想と同じという意味で解説しました(本来は参考文献を出すべきですが、どこに何が書いてあったか忘れました。ということであくまで感想です笑)

楽観の境地である「明日は明日の風が吹く」をガチで体現している狩猟採集民にうつ病がゼロなのも納得!
そして同時になぜシリコンバレーの起業家の間で瞑想がブームなのかもわかる気がします。みんなお金は腐るほどあるけどメンタルボロボロで「本当の幸せって何?」と思ってそうだし(知らんけど)。
実は近年、シリコンバレーにおいて起業家でブームになっている(なっていた)ヤバガジェットが存在します。その名も「Muse(ミューズ)」このガジェットこそ、脳波を測定して誰でも簡単に瞑想の出来不出来を可視化できるという画期的なデバイス。
↓「7割が諦める」瞑想にテクノロジーで挑戦するヘッドバンド↓

以下の動画で瞑想デバイス「ミューズ」を解説しています
↓具体的な瞑想のやり方を詳しく知りたい方はこちらで解説しています↓
最強のメンタル強化方法とは?勝負で勝つ瞑想、マインドフルネス入門

そして、こんな面白い実験が存在します。
よく言われる「病は気から」という慣用句。

ウィスコンシン大学マディソン校心理学部教授リチャード・デヴィッドソン博士が行ったMRIを使用して瞑想が体にどのような変化をもたらすかを明らかにした実験。
この実験結果がおもしろく、なんとインフルエンザの症状と疥癬、つまり水虫の症状を瞑想するだけで改善できたことが数値ベースで報告されました。
この研究が意味することこそ、病は気から。心とカラダは繋がっており、気持ちで免疫力がアップするという事実です。
ちなみに
この結果が信じられなかったので、わたしたちは同じ実験を二回行いました
とデヴィッドソン博士は言っています。
これらの研究を踏まえ、この本ではかなり示唆深い指摘がされています。
瞑想についての研究だけでなく、一般的な神経科学の研究からも発せられる強烈なメッセージは、わたしたちは直接的な精神修養、つまりメンタルを鍛えることによって脳を望み通りに形成できる、というものだ。
一見うさんくさい瞑想やマインドフルネスも実は結構研究がすすめられているのです。最後にひとつ付け加えるとすると、瞑想は簡単なようでいて実際の難易度はかなり高いです。

Philadelphia, United States – July 23, 2016: Weekend scene at the University of Pennsylvania campus
ペンシルべニア大学の心理学者ジョシュア・スマイス博士によれば、「7割の人が挫折する」と指摘し、瞑想ブームに懸念を示す研究者もいるくらいです。
そしてスマイス博士は瞑想するよりも自然と触れるほうが再現性が高いことも指摘しています。詳しくはこちらをご覧ください。
【初心者ランナーにこそおすすめ】なぜトレイルランで足が速くなるのか?
「瞑想ばかりがもてはやされている。ちょっと行き過ぎだよ」
ペンシルべニア大学の心理学者ジョシュア・スマイス博士の瞑想への批判の話はこの本から引用。
今回はあくまで自分の言葉で簡単にかみ砕き、まとめただけなので、少しでも気になった方は是非、本書をお取り下さい。
「人間は、地球上で最も耐久力のあるランナーだ。そう、最強なのだ」はp29
日本でも売れに売れた「脳を鍛えるには運動しかない!」の著者であるハーバード大学院准教授の隠れた?名作。多岐にわたる興味深い知識がエビデンスベースで散りばめられ、現代の常識を疑える示唆に富む良書。出典がついていないのだけが残念(英語版にはあるのか!?)。個人的には最終章にあるリチャード・マニング氏の体験談が面白かったです。個人的には日本語版のあとがきもGOOD(ジェフ・ボレック博士の興味深い研究などが明示)!
↓世界的ベストセラーの代表作↓
【一万時間の法則】10000時間の走り方【ランニング・マラソン・ジョギングで使えるおすすめ心理学】






































コメント