
みなさんどうも、こんにちは!
僕は元帰宅部の本気【The VO2 MAX RUN】というYOUTUBEチャンネルでランニング・マラソン情報を発信をしている市民ランナーです。


ここに1本の論文があります。それがこれ。
2011年のJournal of Strength and Conditioning Researchに掲載されたEnoksen博士らの研究です。この研究から示唆されたこと。
それは有酸素運動レベルでのゆっくり長く走るトレーニングとその反対の比較的短くきついトレーニング。このふたつを比べた結果、比較的短くきついトレーニングがパフォーマンス向上には効果的であるということ。さらに言えば、溜まった乳酸を処理できなくなるレベル、乳酸閾値(いわゆるLTレベル)でのトレーニングが最も効果的であるということ。
【フルマラソンおすすめ練習方法】50を過ぎても速く! FAST AFTER 50 【持久力の科学】
この研究を受けてこの本、Fast After50の著者であり、科学的トレーニングの申し子、TrainingPeaks.comの創業者、ジョー・フリールはこう言っています。
ゆっくり長く走るLSDだけのトレーニングメニューは、ベテランの持久系アスリートにとって、ほとんど効果がなく。有酸素性体力の向上はおろか、何年間か維持することさえできないということである。
そう、彼の結論。
それはタイムを狙うランナーにとって、ロングスローディスタンス(いわゆるLSD)などのゆっくり走るトレーニングに効果は”ほぼない”ということです。
↓この考えの根拠となった論文はこちらです↓

翻って、スロージョギングを提唱した運動生理学者であり医学博士である田中宏暁博士はこの本、「仕事に効く、脳を鍛える、スロージョギング」でこのように指摘しています。
【仕事の効率を上げる】仕事に効く 脳を鍛える スロージョギング【有酸素運動の効果】
スロージョギングは通常のランニングと同等の持久力向上効果をあわせもつという、プロのアスリートの間でも注目されているトレーニング法なのです。
スロージョギングが通常の持久力向上と同じ効果をあわせもつ。しかもこの文脈では全くの素人ではなくプロのアスリートでもその恩恵が得られる。

ジョー・フリールの意見と田中博士の意見

タイムを狙うランナーにとってLSDは効果がほとんどなく、逆に田中博士の提唱するスロージョギングでは効果がある

お互いにゆっくり走っているはずなのにです

なぜそんな違いが生まれるのでしょうか?
本日は、そんな疑問。
なぜスロージョギングでは走力が上がり、なぜゆっくり長く走るLSDでは走力が上がらないのか?スロージョギングで結果を出せる人と出せない人の違いはどこにあるのか?
つまり、パフォーマンスをアップさせるための「真の有酸素運動とは何か?」という視点で誰も考えてこなかったスロージョギングとロングスローディスタンス(LSD)の本質を深ぼっていきたいと思います。

この動画をブログを最後まで見ると、スポーツ科学から見た真の有酸素運動の正体とその具体的な方法がわかる。おそらくここまで深ぼった解説はないと思いますので、是非、最後までご覧ください。
目次
真の有酸素運動とはゆっくり走るAeTトレーニング

早速、結論です。
それは、スロージョギングとロングスローディスタンス(LSD)は実は本質的に別物である可能性が高いからです。
そして、このスロージョギングとLSDをごちゃごちゃにして考えているため、走力が上がらなかったり、結果を出せなかったりするのではないのか?
とこれだけ聞いても、ピンとこないはずなので、具体的にわかりやすく解説します。
スロージョギングとLSDの本質的な違い。正直、とてもシンプルです。その違いは「ゆっくりさ」です。

パフォーマンス向上の鍵。真の有酸素運動とは何なのか?
もしあえてこの難問に答えるのなら、答えはやはりこれです。
AeTもしくはAeTトレーニング
このAeTという三文字のアルファベット。

おそらくほとんどの方が聞いたことがない専門用語だと思います。
それもそのはずで、この専門用語を含むLT・いわゆる乳酸閾値という言葉はガチの研究者であっても勘違いしてしまう、もしくは誤解してしまう代物であると、先程のジョー・フリールは指摘しています。
ではこのAeTという言葉がついたトレーニング、AeTトレーニングとは一体どんなトレーニング方法なのでしょうか?
一言で言えば、比較的ゆっくりと走るトレーニングです。そしてこれこそがスロージョギングとLSDを分ける考え方です。

そう、スロージョギングとLSDを分ける違いがゆっくりさでした。

この「ゆっくり」というのがどれくらいゆっくりなのか?その具体的な数値を生理学的に表すのがAeTという言葉なのです。
AeT(Aerobic Threshold)有酸素性作業閾値とは何か?

AeT(Aerobic Threshold)の日本語訳はズバリ、有酸素作業閾値もしくは有酸素性作業閾値。
「えっ、それは」とおもった方は鋭いです。その通り、一般に言われるLT(乳酸閾値、乳酸性作業閾値)といわれる値。この言葉も厳密にはなんと同じく有酸素作業閾値と呼ばれることもあるのです。
これが研究者も勘違いしてしまう元凶なのです。
この本、FastAfter50ではこう指摘されています。
さらに複雑なのは、LTには2つあるということです
この本の言葉を借りると、きわめて低い強度で起こる乳酸値の上昇と、ある程度の運動強度で起こる乳酸値の上昇。このふたつがLT(Lactate Threshold)乳酸閾値という言葉に凝縮されており、混乱を引き起こしているのです。
つまり何が言いたいかと言うと、LTやLT値と呼ばれるひとつの言葉には実は全く違うふたつの意味が含まれているということです。
そして通常LTという言葉は上の値、ある程度の運動強度で起こる乳酸値の上昇のことを指す場合がほとんどです。LTトレーニングと呼ばれるトレーニングがゆっくり走る、鼻歌が歌えるレベルのトレーニングではないことは中級者以上のランナーなら体感的に理解しているかと思います。

それこそがAeTトレーニングなのです。
そして、このAeTトレーニングの運動強度こそ、実は田中宏暁博士が提唱しているスロージョギングと呼ばれるエクササイズの運動強度であり、有酸素運動と言えば、その代表格である理論、マフェトン理論。
このマフェトン理論の提唱者であるフィリップ・マフェトン博士が指摘する有酸素運動強度の理想もおそらくこのAeT強度だと思われます。
つまり僕が言いたいことは、スロージョギングやマフェトン理論とロングスローディスタンス(LSD)は実は本質的に別物である可能性が高く、その違いがAeTと呼ばれる乳酸閾値を基準とした数値であるということです。
言い換えると、スロージョギングはAeTトレーニングであり、LSDはAeTトレーニングではないということです。
あまりピンとこない人のために、もっとかみ砕くと、比較的遅いトレーニングがAeTトレーニングであり、さらにその下のめっちゃくちゃ遅いトレーニングがLSDである。そのような感じで捉えてください。
そしてパフォーマンスが上がるのがAeTトレーニングであり、LSDなどのAeTの強度を管理できていないめっちゃくちゃ遅い、ゆっくりさこそが全ての元凶となり、LSDではパフォーマンスの向上が見られないのではないのか?ということです。

冒頭での質問

なぜスロージョギングでは走力が上がり、なぜゆっくり長く走るLSDでは走力が上がらないのか?スロージョギングで結果を出せる人と出せない人の違いはどこにあるのか?

答えはズバリ、ゆっくり走るの「ゆっくり」を管理できていないからと言えるのかもしれません。
ということで改めてゆっくりとは何かをより具体的に定義したいと思います。
そして、先ほどから説明している仮説やこれから話す定義はあくまで複数のランニング書籍や論文を読んで導き出した一素人の考えですので、その点だけはご注意ください。
ゆっくり走るとは何か?スロージョギング、スローなランニングの定義

スロージョギングとLSDの厳密な分かれ目は血中乳酸濃度です。
2mmol。この数字です。
LSDは血中の乳酸濃度2mmol未満の運動をさし、スロージョギングは血中の乳酸濃度2mmol以上の運動をさします。

そう2mmol未満か2mmol以上です
この2mmolという数値こそ、何を隠そう乳酸値が最初に上昇する低い方のLTの値。つまりAeTの値です。
AeTトレーニングは血中の乳酸濃度が2mmol以上のゾーンなのです。

と言われてとまったくピンとこないのは、僕も同じです
AeTトレーニング(血中乳酸濃度2mmol以上の運動)の仕方

ということで、具体的にわかりやすくこのAeT、2mmol以上の運動を把握する方法をお伝えします。
AeTは心拍数をベースにして測定します。よって詳しいAeTゾーンを知りたい方は心拍計が必須となりますので、是非とも購入することをおすすめします。そんなに高価なものではありませんし、なんならアップルウォッチなどでも測定できます。
日常でも運動でも使えて高級腕時計の代わりにもなる個人的にコスパ最強の腕時計
↓僕も愛用しています↓
↓そしてなんと不安やうつなどのメンタルヘルスの管理にも心拍数は活用できます↓
【うつ病も治る!?】有酸素運動と高心拍トレーニングはなぜおすすめなのか?
では、話を戻して、心拍計を使ったAeTの把握の方法をお話します。

AeTトレーニングとは何ぞや?そう問われると、解答としてはこうなります。

これです。
この最大酸素摂取量、VO2MAXの60%とは、心拍数に換算すると最大心拍数の約70%の運動をさします。
では、まず一番最初にすべきこと。それは20分間のタイムトライアルです。

そうです。20分間本気で走ってみてください。
ワンポイントアドバイスとしては、5kmや10kmの短めのレースを活用します。
レースではアドレナリンが出て、全力を出しやすくなります。20分間でどれだけ前の人を抜かせるか、あるいは集団から落ちずに走れるかを目標に全力で走り、20分経過したら、あとは流してゴールすると良いデータがとれると思います。
そしてその20分間のタイムトライアから導いた平均心拍数から5%を引いた数値がLT心拍数と呼ばれる数値です。

このタイムトライアルから算出したLT心拍数からさらに30bpmを引いた数値こそが、今回のメイン、AeTの予測値です。

FASTAFTER50によれば、この計算方法でかなり正確なAeTが求められるとのこと
次にこの式で出したAeTに2bpmを足した数値と、5bpmを引いた数値を出してみてください。この足し引きの数値の幅でAeTゾーンが判明します。
たとえば、20分間のタイムトライアルでLT心拍数が150bpmだとわかった場合はそこから30引くと120bpm。そこに2bpmを足した数値と5bpmを引いた数値。それが118bpm~125bpm。

これがトレーニングゾーンとなります。このゾーンはシーズン中に体力が向上しても一定です。
わかりやすいAeTを計算する方法4ステップ
ステップ②LT心拍数を計算
ステップ③AeTを計算
ステップ④AeTトレーニングゾーンを計算
ステップ①20分間の全力タイムトライアルで平均心拍数を測る
ステップ②LT心拍数を計算
20分間タイムトライアルの平均心拍数‐5%=LT心拍数
ステップ③AeTを計算
LT心拍数‐30bpm=AeT
ステップ④AeTトレーニングゾーンを計算
AeTゾーン(トレーニングゾーン)
AeT+2bpm=上限値
AeT-5bpm=下限値
【具体例】AeTの求め方

ステップ①20分間のタイムトライアルで平均心拍数を測定
平均心拍数が185bpm(回/分)の場合
ステップ②LT心拍数を計算
185×0.05=9.25(5%の値)
185-9.25=175.75
よってLT心拍数は【176bpm】※四捨五入して※
ステップ③AeTを計算
176‐30bpm=146bpm
よってAeTは【146bpm】
ステップ④AeTトレーニングゾーンを計算
146+2bpm=148bpm
146‐5bpm=141bpm
よって、AeTトレーニングゾーンは【141~148bpm】
↓詳しく知りたい方はこの科学トレーニングの名著がおすすめ↓
「ゆっくり走る・スロージョギング」真の有酸素運動AeTって何?


もう一度おさらいしてみましょう
AeTトレーニングとは最大酸素摂取量60%以下の運動を指します。
そして、その最大酸素摂取量60%の運動の求め方は、20分間の本気走り、タイムトライアルから算出できます。20分間のタイムトライアルでの平均心拍数から5%を引いた数値。これがLT心拍数と呼ばれる値です。このLT心拍数からさらに30bpmを引けばOKです。

これでかなり正確なAeTの数値が出てきます
ちなみにこれはベテランのシリアスランナーやシリアスアスリートの場合なのですが、初心者ランナーであってもこの基準値を適応してもいいかなと個人的には考えています。というのも、AeTトレーニングは血中乳酸濃度2mmol以上の運動強度が求められているので、強度を減らして2mmol未満にしてしまうとそれこそLSDと同じになりせっかくの運動での恩恵がかなり少なくなるからです。
それであれば、やや運動強度が高い2.5mmol程度など高い数値になったほうが、AeTの恩恵は確実に受けられると考えるからです。ちなみに高すぎるのもだめなので、出来る限りドンピシャ2mmolが最も効率が良いと思われます。
正直、専用の乳酸値測定の器具を持っていないと正確な測定ができないため、かなり難しいのが現実ですが、それは仕方ありません。
そして、こうして出したAeTの心拍数をベースにトレーニング、走り込みを行います。
ゆっくり走るAeTトレーニングがおすすめなもうひとつの理由

とAeTトレーニングの恩恵はなんとこれだけではありません。このAeTがおすすめなもうひとつの理由。

それがこれ。

体力の向上をしんどい思いをせずとも、かなり正確に把握できることです。
実はこのAeTという数値はEFと呼ばれる効率性を測定するのに最も適した強度なのです。
このEF・効率性とは、ある速度やパワーを生み出すのに、どれだけの運動努力やエネルギーが必要かということであり、持久系競技の体力指標としては、最も正確なもののひとつです。
EFを測定するには、たとえば、週に1回、同じコース、同じウォーミングアップ、同じ心拍数レンジ(つまりAeT心拍数±2~5bpmゾーン)でテストするのです。できれば気象条件や実施時間もそろえた方がベストです。
そしてその数値を出来れば長期間、具体的には8週間程度、つまり8回継続して測定し、全体的に見てEF・効率性が上昇していれば、体力が向上していると判断できるのです。※一時的に走力が低下する場合も多いので、あくまで長期視点で把握することをおすすめします※

おそらくこの効率性、EFを測定する方法が体力の向上を知る上でゼエハアと息を切らす必要もないため簡単で尚且つ正確なのでおすすめです。
ゆっくり走るAeTトレーニングは脂肪の燃焼や毛細血管の増加もできる

AeTトレーニングのメリットはこのように体力の向上を正確に知る方法以外にも、LSDでよく言われる脂肪の効率的な燃焼や毛細血管の増加も同様に期待できます。
さらに腎臓でつくられるエリスロポエチンという名のホルモンの分泌量を増やすことができ、赤血球の数が増えます。赤血球が増えるということは、酸素を筋肉に運搬する能力が高まるということです。
こうしたことはすべて1つの運動、つまり、長時間、中程度のゆっくり強度で行う持続的なAeTトレーニングから生まれる結果なのです。
だからこそ、ジョー・フリールはAeTトレーニングについてこう指摘しています。
AeTトレーニングはLSDに良く似た練習と言えるかもしれませんが、LSDと大きく違うのは、ふつうのLSDの「SLOW」の部分が、あまり遅くないという点です。
さらにこうも指摘します。
実はこのタイプの練習効果の1つに、低強度での速度が大幅に向上する、ということがあります。
そうなのです。LSDのトレーニングではこのような低強度、つまりジョギングでの速度が大幅に向上することがほぼほぼないため、彼はLSDを否定し、AeTを肯定しているのです。
そして、このAeTを使った練習を「LMD(Long Moderate Distanace)」あるいは「LSD(Long Steady Distance)」と呼び、通常のゆっくり長く走るLSDやジョギングの変わりとして組み込むことを提案しています。
さらに彼はこのようなアドバイスもしています。
競技継続時間が30分程度までの種目ならば、LTよりもVO2MAX強度のトレーニングのほうが、効果が高いと考えられます。30分か2時間程度の種目ならば、逆にLT強度の練習を中心に行ったほうがよいでしょう。
そしてこう続けます。
2時間以上かかる種目ではVO2MAXとLTを適切にブレンドしようとすれば、やはりLTに傾いたものになります。しかし、こうした種目に欠かせないのは、AeTを中心にしたトレーニングです。種目の時間が長くなるほど、AeTに比重を置くべきなのです。
そう、種目の競技時間が長くなれば長くなるほど、AeTに比重を置くべきなのです。

これが走り込み、距離を踏むということ。トレーニングの前提となる部分です。
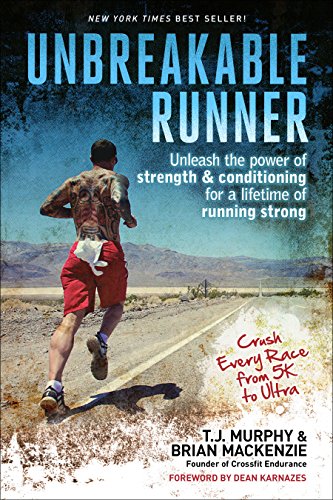
有酸素運動と無酸素運動を効果的に組み合わせることが高度なフィットネスパフォーマンスの鍵だ
この言葉。著述家でフィットネストレーナーのブライアン・マッケンジーの言葉です。

この有酸素運動に当てはまる大部分がAeTトレーニングということになります。
【具体例】AeTトレーニングの量はどれくらいがいいのか?


ということでもっと具体的にお伝えします。
もしあなたが何かしらのレースに参加するのなら、
目標タイムが4時間を超える場合なら、AeTトレーニングの継続時間は【2~4時間】がおすすめです。
目標タイムが2~4時間ならば、AeTトレーニングの継続時間は【1~2時間】を目安にしてください。
目標タイムが2時間未満ならば、AeTトレーニングの継続時間は【30分~1時間】がベストです。
このように走り込みであるLSDやジョギングの部分をAeTトレーニングに変更することで、真の有酸素運動、つまりゆっくり走っても、パフォーマンスが向上する可能性が高まります。

これこそが真の有酸素運動の活用の方法!

とここまで聞くと、AeTは思ったほどスローではないような気がしてくると思います。
実際に先程のジョーフリールの発言、彼は
AeTトレーニングはLSDに良く似た練習と言えるかもしれませんが、LSDと大きく違うのは、ふつうのLSDの「SLOW」の部分が、あまり遅くないという点です
と言っています。
しかし田中博士のおすすめするスロージョギングはかなりゆっくりとしたペース、具体的には1キロ8分34秒ペース以下を指定しているため、矛盾が生じているように思います。
【初心者こそ上級者用シューズがおすすめ!】スロージョギングで人生が変わる
【徹底解説】ランニングする前に読む本 マラソンの科学的トレーニングとは?

しかし、なんとスロージョギングでもこのAeTは再現できる可能性が高いのです。
おそらくその理由はピッチ数に隠されているのではないかと僕は考えています。田中博士は
高回転のフォアフット走法でスロージョギングを行いましょう!
とアドバイスをしてくれています。

まるで足踏みをしているかのように進むのです。

この高回転のピッチ走法がミソなのです。スピードは遅いかもしれませんが、その分脚を動かすことで、乳酸は確実に溜まっていきます。
だからこそ、スピード自体は遅いですが、AeTトレーニングレベルまで運動強度を上げられる可能性があるのです。
そして、ここからより大胆に仮説を展開していくと、スロージョギングで走力が向上した人や結果を出せた人は、このAeTレベルでのトレーニング、田中博士が意図している運動強度のドンピシャかそれより若干高めの運動強度を上手く再現できたことで、血中の乳酸濃度を2mmolを少し超える程度の良いラインにのせることができた。
すると、AeTトレーニングの特徴である「低強度での速度が大幅に向上する」という恩恵を無意識に受けることで、軽いランニングのスピードが大幅にアップし、フルマラソンのタイムが爆上がりした。もしくはプロアスリートであれば、土台の強化に繋がるためにパフォーマンスの向上に一役買った。

これがLSDでは走力アップは出来ないが、スロージョギングでは走力アップが出来る、スロージョギングで成果を出せたカラクリとして僕が考えた仮説です。
スロージョギングやマフェトン理論が失敗してしまうその理由

正直なところ、現在、田中博士が提唱しているスロージョギングやマフェトン博士が主張したマフェトン理論はそこまでメジャーではありません。それはおそらく失敗した人、成果に繋がらない人が数多くいるからだと思います。
実はこのふたつ、スロージョギングとマフェトン理論に共通するある致命的な落とし穴のためだと思われます。

スロージョギングとマフェトン理論に共通するある致命的な落とし穴とは一体何なのか?

そう、それが心拍数の公式です。
運動強度、運動のきつさを示す指標として心拍数を用いたことが良い意味でも悪い意味でも田中博士やマフェトン博士の致命的な落とし穴に繋がっているのではないかと僕は考えています。
たとえば、田中博士なら運動強度・運動のきつさの目安を以下の公式で表したり(目標心拍数=138ー年齢/2)、マフェトン博士ならこのような公式(目標心拍数=180-年齢など)で誰でも簡単に測れるようにしました。

この発想自体はかなりわかりやすく、素晴らしいことなのですが、運動のパフォーマンスを上げるのに重要なのはあくまで血中の乳酸値、乳酸濃度です。
そして、この2mmolという乳酸値が人によって全然違うため、ある人には鼻歌が歌えるレベル、ある人にはやや息がつまるレベルだったりと個人差も大きく、もしそのギリギリ2mmolを狙って運動強度をコントロールすると画一的な心拍数というものさしではその個人差を測ることができません。

つまり、心拍数の公式では個人差をほとんど考慮できないのです。
よってある人には公式通りの運動で2mmolのラインにのせれたが、別の人では同じ計算式でも1.8mmolだったりするわけです。
これが成果が出せる人と出せない人、パフォーマンスが上がる人と上がらない人の究極的な違いだと考えます。
この誤差が招く失敗が、
スロージョギングやマフェトン理論をやってみたけど全く効果がなかった
といわれる由縁であるように僕は感じています。
さいごに

さいごにまとめとして、40歳を過ぎてからフルマラソンを2時間20分弱のタイムで走り、50歳を過ぎてからも2時間30分弱のタイムで走った伝説のニュージーランドのマスターズランナー、ロジャー・ロビンソンの言葉を取り上げておわりたいと思います。
彼はこう言っています。
われわれランナーは、練習量を減らし、練習をしすぎず、体を壊す前に自重し、楽に短い距離を走るよう警告されている。これらの警告に対して、科学的根拠に基づいた私のコメントは、”くだらない”だ。スローなランニングは、スローな走りをトレーニングするだけだ。
そして彼はこう続けます。
走り込まなければレースの質を下げることになる。軽いランニングは楽しいだろう。健康にもいいし、多くの人々にとってエクササイズとして最適なレベルかも知れない。しかし、そんなランニングをしていては、あなたとライバルとのギャップは埋まらないんだ。
この発言で彼が言いたいことは、タイムを追う者にとってLSDなどのスローなランニングの効果は低く、ある程度のスピードで走り込まなければいけないということ。
もうひとつは、タイムを追うランナーとそうではないランナー、つまり本気のランナーと健康志向のランナーであれば、ランニングの価値観ももちろん違って当たり前ということです。
LSDがおすすめなのは健康志向のランナーやフルマラソン完走を目指すランナー

ゆっくりと長い距離だけを走る健康志向のランナー。その目的が健康の維持・向上、もしくはフルマラソンの完走ならば、LSDはとても良い選択肢です。が、しかし、少しでもタイムを追いかけるランナーであれば、LSDだけでは通用する可能性が低い。
彼が言う、「走り込みをするのなら、スローではないランニングをしろ!」

この文脈ではその運動強度こそがおそらくAeT以上の強度なのです。
何が言いたいかと言うと、往年のレジェンドランナーであるロジャー・ロビンソンもジョー・フリールと同じでゆっくり走るLSDトレーニングに否定的であり、少なくとも走り込みにはある程度の運動強度が必要であるということです。
【補足】スロージョギングやマフェトン理論などが本当の正解ではない

とここでひとつだけ超重要な補足をしてこの話を終わりたいと思います。
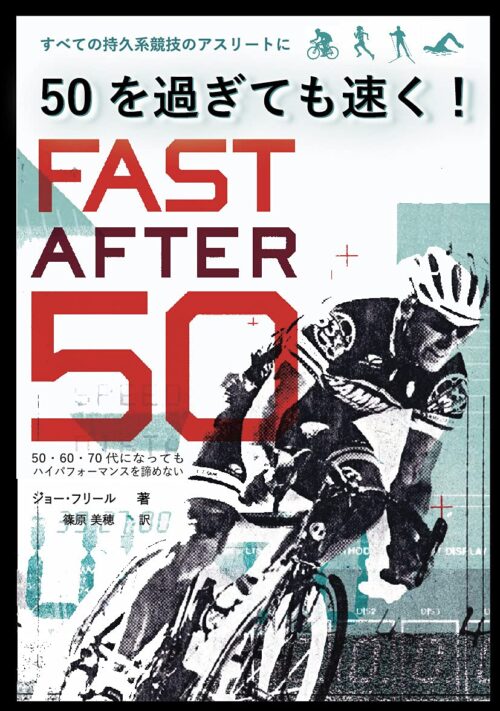
それがこのふたり、ロビンソンやフリールの価値観・考え方はバリバリの西洋モデルということです。
この本、「マラソンはゆっくり走れば3時間を切れる!49歳のおじさん、2度目のマラソンで2時間58分38秒」で紹介されているゆっくり走るという考え方。これは東洋的な考え方。いわゆる「はりやお灸」と言った鍼灸、つまり東洋医学的な見地からゆっくり走ることが推奨されています。
さらに日本でのLSDの生みの親である佐々木功監督が書いたこの本。「ゆっくり走れば速くなる マラソン㊙トレーニング」での自分と対話をする方法としてのLSDであったりと、メンタルの部分に焦点を当てたLSDも存在します。
スローなランニングに対するロビンソンの発言。
科学的根拠に基づいた私のコメントは、”くだらない”だ
この言葉での違和感。運動生理学的な変化だけを捉える西洋的な価値観だけを持ってスローなランニングを一刀両断するのは言い過ぎであり、AeT強度に満たないゆっくり長く走るLSDにもメリットは存在すると個人的には考えています。

知識とはマクロな視点・巨視的な視点を提供してくれるものです。できるだけ多様な価値観・多様な意見を知ることで、総合的に評価していきましょう。

答えは本の中にもコーチの頭の中でもなく、自分の頭、自分の体の中にしかありません。
ゆっくり走ることを体系的に理解するためにこのトピックに関しての関連動画を見てみて、すべてを知った上で自分にとって何が良いのか何が悪いのかを是非ともご自身の頭で考え、ご自身の体の中にある最適解を導き出してみてください。

上にスクロールして文章中にある動画も是非ご覧ください!
↓その他関連ブログ・動画↓
【ジョギングの生みの親】リディアードのランニングトレーニング
【ランニング初心者は必見!】強い心を手に入れるメンタルトレーニング【メンタルが強くなる方法】

































コメント